士業の新しい営業方法を提案!他士業との協力でビジネスは展開できる
-
公開日:

「自分の価値が下がるから士業は営業すべきでない」
「営業する士業は売上が無いって言っているようなものだ」
私自身、士業を生業として仕事をしていますが、このような声をよく耳にします。
確かに「先生」と呼ばれることもある職業なので、積極的に営業をすることに抵抗を感じる人も多いと思います。
しかし、そうは言っても、安定した仕事・安定した売上のためには営業活動は不可欠です。
何もせずに、仕事が降ってくることはほとんどありません。
よほど差別化され、専門特化された業務を請け負うことができるのであれば営業は不要ですが、多数の士業の独占業務は定型化されたものであるため、どうしても同業内で競争が発生します。
その競争の中で勝ち残って行くためにはやはり、営業が必要です。
しかし、士業従事者でゴリゴリの営業ができる人は数少ないでしょう。
そこで今回は、そんな士業向けの新たな営業方法についてお話しします。
新規顧客を獲得したいが、営業力に自信がないという士業従事者にピッタリな内容となっていますので、ぜひ最後まで読んで実務にお役立てください!
それではまずは、この記事のまとめからです。
今回の記事まとめ
①士業でも営業をしなければ生き残れない
②他士業と協業することでビジネスの幅が大きく広がる
③トータルの士業サービスを確立し、営業ツールとすることで新規の案件を獲得できる
この内容について詳しく解説していきます!
(編集 安藤駿)
目次
士業の現状
〜士という資格ってたくさんありますよね。
この記事はどのような士業向けの内容になっているのでしょうか?
たしかに、〜士とつく資格はたくさんあります。
今回の記事は、その中でも10士業向けとなっています。
10士業?初めて聞きました。
説明をお願いします。
わかりました。
それでは、まず10士業について紹介します。
10士業とは?
10士業という言葉は確かに聞き慣れない言葉かもしれません。
10士業とは商工会議所の相談窓口に設置されることが多い、10種類の士業のことです。
具体的には以下のようになっています。
10士業一覧
| 名称 | 業務内容 |
| 司法書士 | 相続、遺言、登記代理など |
| 行政書士 | 契約書類の作成代理など |
| 土地家屋調査士 | 土地分筆など |
| 弁理士 | 特許など知的財産全般 |
| 公認会計士 | 会計、監査、経営など |
| 税理士 | 税金全般 |
| 社会保険労務士 | 人事・労務関係、年金など |
| 中小企業診断士 | 創業、経営など |
| 不動産鑑定士 | 土地の評価など |
これらの資格はいずれも難関の国家資格であり、私も「中小企業診断士」の有資格者です。
世の中にはダブルライセンス、トリプルライセンスを取得している方もたくさんおります。
(私はもう試験勉強は無理です。。燃え尽きました。真っ白に。。)
ちなみに、弊社所属コンサルタントの横井ゆきえさんはトリプルライセンサーの一人です。
(まさかこんなに身近にいるとは思いませんでした。)
独占業務があろうとなかろうと弱者と強者は生まれる
さて、上記のほぼ全ての国家資格には「独占業務」が存在します。
独占業務とはその有資格者でないとできない法律で定められた業務のことです。
この参入障壁により、各国家資格は高度に専門化され、また業務遂行が可能となっています。
しかし、冒頭にもお話ししたように独占業務があるといっても、どうしても競争力に差が生まれてしまいます。
さらに言えば、私の保有する「中小企業診断士」には、独占業務がありません。
厳密に言うと無くはないのですが、生業とするには少なすぎます。
これは、中小企業診断士は幅広い経営知識を持った診断・助言が業務となり、これを独占業務にすることは難しいためです。
このように、独占業務のない高度な知識を持つ士業も中にはあります。
当然、独占業務の障壁の中でも競争力の弱い士業や、中小企業診断士のような独占業務のない士業は、パワーのある士業や企業に顧客を取られやすくなります。
では、競争力の弱い士業や、独占業務のない士業の従事者はどのようにして顧客を獲得すればいいのでしょうか?
そういった士業従事者は細々と業務をすることしかできないのでしょうか?
この問題に対して、私は明確に「否」と答えます。
なぜなら、中小企業診断士やその他強者とは言えない士業は、専門特化された他士業との協業によって、新たな展開を企業様に示すことでビジネスの幅を広げられると考えているからです。
他士業との協業、、
これはどういうことでしょうか?
それでは次に、他士業との協業について詳しく説明します。
士業同士で協業することでより高度なサービスを提供できる
士業同士で協業するってYouTuber同士のコラボ動画みたいなものでしょうか?
ざっくり言うとコラボ動画でYouTuberがやりたいことと一緒です。
厳密に言うと、士業同士で協力することで業務の幅を広げ、新たなビジネス・高度なサービスを提供できるようになるということです。
わかりづらいと思うので具体例をもとに、解説していきます。
例1:税理士と司法書士で協業
新会社設立・増資・合併、相続・遺言等の業務をワンストップで対応可能
例2:司法書士と土地家屋調査士で協業
不動産登記業務の効率化(こちらはすでにかなり密接に協業している)
このように、他士業と連携することにより、自身の士業ビジネスの可能性は飛躍的に広がることがお分かりいただけると思います。
それでは、他士業の従事者とどのように繋がり、協力関係を築けばいいのでしょうか?
他士業とつながるのは難しそうなイメージがあります。
どのような方法がありますか?
確かに、同じ士業というジャンルでも違う資格なら異業種と一緒。
次は、他士業とつながる方法についてお話しします。
他の士業とつながるためには?
他の士業と協業すれば、ビジネスの幅を広げることができます。
しかし、「そもそも他士業とつながるための方法が難しい」と思われる人が多いと思います。
ここからは他士業とつながるための方法を説明します。
他の士業とネットワークがない場合
まずは、そもそも何もネットワークがない場合を考えてみましょう。
この場合は、まず自身のウェブサイトやSNSで情報発信を行うのが良いかと思います。
特にSNSはどんな資格を持っているかや、どのようなモチベーションで働いているかがわかるので積極的に活用するのがオススメです。
私のツイートも先日プチバズりました。
そのツイートがこちら。
コロナ禍に中小企業診断士として独立し、とりあえず半年で毎日めちゃ楽しい仕事しながらサラリーマン時代の1.5倍の収入までなった。どうしたら診断士として充実した人生を送れるかをTwitterを通して今後発信して行くことで、診断士の独立のハードルを少しでも下げられたらと思っています。
— 水上竜児@営業強化したい会社のための中小企業診断士 (@ryujim725) January 8, 2021
他士業とネットワークがわずかでもある場合
次は、少しでも他士業とのネットワークがある場合です。
直接会ったことがなかったり、深く話したことがなかったりしても、なにかしらもネットワークには属していることがあると思います。
そのような場合は、どんどん他士業の人と関わりを持つような取り組みをするべきです。
自分から絡みに行くのは億劫なことかもしれませんが、自分のためだと思って、積極的に関わりを持っていきましょう。
なるほど、このように頑張ってつながりを持つことができたら次は何をすればいいでしょうか?
他士業との関わりを持つことができたら、あとは提案をするのみです。
しかし、「こういうのやったら面白いんじゃないか」レベルの提案では協業するのは難しいでしょう。
相手からしたら、今までやったことがないことをするので、抽象度の高い提案では協業しようという気になりませんよね。
そのため、具体的で実現可能性の高い提案をする必要があります。
確かに、具体的な提案をしないと納得してもらえませんね。
はい、納得しないと人は行動を起こしません。
そこでここからは、相手に納得してもらうための提案をする方法を解説します。
他士業にどのように提案すれば良いのか?
他士業に協業してもらうための方法として、まず心がけるべきことは「彼を知り己を知れば百戦殆からず」です。
つまり、こういうことです。
①市場のニーズを理解する
②他士業の資格を分析する
③自身の資格も振り返る
このようなプロセスを踏むことで、何が提案できるかが見えてきます。
例えば、中小企業診断士周りの話をしますと、現在コロナによって中小企業の業績が低下し、事業譲渡のニーズが高まっており、事業譲渡の相談を中小企業診断士が請けたとします。
中小企業の事業譲渡〈いわゆる「スモールM&A」〉は、大手M&A会社様はなかなか対応できません(①市場のニーズの理解)。
そのため、「スモールM&A」に早期対応することは中小企業診断士としての急務でしょう。
この場合、デューデリジェンスやリーガルチェックが必要になりますが中小企業診断士では、それらに関わる業務ができません(③自身の資格も振り返る)。
そこで、デューデリジェンスは税理士、リーガルチェックは弁護士が得意としているため、そのような士業との協業が考えられます(②他士業の資格を分析する)。
あとは、企業の人事・総務面の業務を社労士、届出関係業務を行政書士(②)といったように様々な士業と協業できる可能性があります。
投資を行うにあたって、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査すること(SMBC日興証券 「初めてでもわかりやすい用語集」より)
弁護士(もしくは法務担当者)などの専門家に契約書の内容に問題がないか、法的に妥当であるかをチェックしてもらうこと(NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社「リーガルチェックとは?弁護士にお願いするメリット・デメリット」より)
これはあくまで一例ですが、それぞれの士業の専門性を発揮したトータルの士業サービスを提案することができれば、その提案に関心を持った他士業と協業できる可能性が高まります。
ここまで、競争力の弱い士業や、独占業務のない士業の話をしてきましたが、そうでない士業でも協業することで今までよりも高度なサービスを提供することはもちろんできます。
トータルの士業サービスを確立し、強力な営業ツールにする
このように、他士業と連携してトータルの士業サービスを確立できれば、非常に魅力的なコンテンツになると思いませんか?
自分の専門領域外のことに関してもサポートできるため、同業者との差別化を図ることがでるのです。
士業としての経歴や実績による競争力が弱くても、トータル士業サポートのコンテンツがあれば、強力な営業ツールになるはずです。
さらに、自身の資格のみでは請けることができなかったであろうダイナミックな仕事を掴む可能性が広がります。
「トータルの士業サービスを確立し、そのコンテンツを営業ツールとして顧問先や新規顧客に提案すること」これが私が提案する士業の新しい営業方法です。
この方法を採用することで、泥臭い営業活動を行うよりも成果を出しやすく、事業の規模を大きくしていくこともできるでしょう。
まとめ
今回は、士業向けの新たな営業方法についてお話ししました。
冒頭にも書きましたが、もう一度今回の記事のまとめを見ていきましょう。
今回の記事のまとめ
①士業でも営業をしなければ生き残れない
②他士業と協業することでビジネスの幅が大きく広がる
③トータルの士業サービスを確立し、営業ツールとすることで新規の案件を獲得できる
中小企業診断士は他士業とのハブ的な役割を担うと考えています。今後は中小企業診断士からの様々な業務提案があるかもしれません!
アクセルパートナーズでは初回60分無料相談を行なっております。
営業方法にお悩みの士業従事者の方々、ぜひお問い合わせください!
編集後記
水上さんのツイート、多くの人の心に刺さったみたいですね。
フォロワーも増えたと聞きました。
はい、ありがたいことに多くの人にフォローしていただきました。
ただ、バズったツイート以降、あまり投稿しなかったため、日に日にフォロワーが減るという経験もしました、、
何事も継続しないといけませんね!
今日も、『元気・前向き・カーキ*』な水上さんでした!
*水上さんは最近、週3回カーキのセットアップを着ています。
詳しい経緯はこちらの記事の「編集後記」をご覧ください。
補助金に関するお悩みは
アクセルパートナーズに
お任せください!
補助金の対象になるのか、事業計画から相談したい等
お客様のお悩みに沿ってご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。


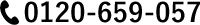
 お問い合わせ
お問い合わせ 補助金無料相談
補助金無料相談