技術と技能は違う!?中小ものづくり企業が技能継承に取組むときの参考事例
-
公開日:
「2019年版ものづくり白書」を参考にしながら、考えてみたいとおもいます。


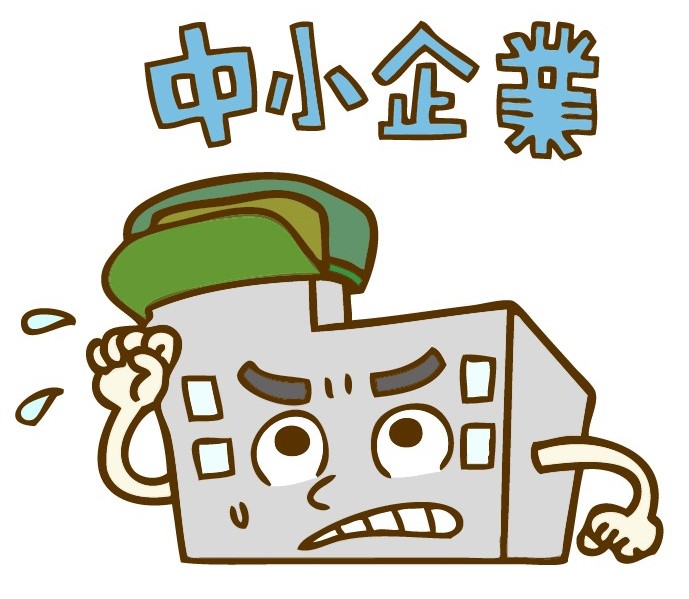


目次
1.技術と技能の違い
「技術の継承」「技能の継承」 あまり区別せずに使っていましたが、ものづくりの現場においては、本質的な違いがあるようです。 ■「技術」 図面、数式、文章など、なんらかの客観的な表現によって記録され伝えられる、形式知を主体にするものであり、その人を離れて、伝達・伝播される ■「技能」 人に内在する、暗黙知を主体とする能力であり、その人を離れては存在しえず、実際の体験等を通じて人から人へと継承される このように、「技能」は人から人へ継承されるので、継承するのに長い時間が必要になります。また、人に内在するため、一度失われてしまうと、容易に復活することができなくなります。 そのため、今後は技能承継の受け手となる人材を確保することと、より効果的な技能継承の取組みに、一層の工夫が必要になってきます。2.技能継承がうまくいっている企業の特徴
中小ものづくり企業では、技能継承がうまくいっていない企業のほうが多いようです。 そこで、技能継承がうまくいっている企業にはどのような傾向があるのか、特徴をまとめてみます。 ≪うまくいっている企業の特徴≫① 労働生産性が高い
技能継承に成功していると、生産性もあがっていると感じている ※労働生産性=生産量÷労働量(労働者数)② 年齢構成(若手・中堅・ベテラン)のバランスがよい
ベテランから中堅へ、中堅から若手へと、技能の受け手と伝え手の年代が近く、円滑に継承を進めやすい③ 採用が計画通りにできている
新卒採用より中途採用を中心におこなっている企業が多く、積極的な採用姿勢がうかがえ、ほぼ計画通りに採用できたと感じている④ 採用できた人材の定着率がよい
技能継承がうまくいっていない企業より、倍近くの割合で、採用できた人材の定着ができている⑤ 女性活躍が進んでいる
うまくいっている企業のほうが、やや女性の活用が進んでいるが、全産業と比べて、ものづくり産業での女性の雇用者割合が1割以上少ないため、産業全体として一層女性の活用に取り組む必要がある⑥ 現場熟練技能者の役割は技能の伝え手
熟練技能者を、現場での作業者として活用すると同時に、技能の伝え手として役割づけをしている⑦ 人材の育成方針の現場への浸透
「もう一段アップできる能力開発」や「数年先の事業展開を考慮した人材育成」など、将来を見すえたものづくり人材の育成や能力開発をおこなう目標を立てており、社内へも方針を浸透させている⑧ ⑦の方針策定、社内浸透による効果
⑦の人材の育成や能力開発方針を社内へ浸透させ、技能継承の重要性が職場内で周知されることで、以下の効果をうみだしている。 ・計画的にOJTを実際に実施する ・伝え手と受け手が良好なコミュニケーションをおこなう ・受け手に高い意欲が培われる⑨ 伝え手の支援
伝え手の確保だけではなく、以下のような伝え手の支援をおこなっている。 ・継承すべき技能の、見える化(テキスト化・マニュアル化・IT 化)を図る ・技能継承の指導者に対して、「教える」ことに関する訓練を実施する ・会社内外を問わず、熟年技能者を講師として勉強会を開催する ・技能承継の指導者を選抜する このように、技能を実際に教えていくために必要な、ツールやノウハウ、体制の整備など、多くの取組みを行っている傾向がある。 ものづくり人材の高齢化や技能継承の取組みのために、さまざまな取り組みをおこなっているなかで、継承すべき技能を明確にして、熟練技能者を引き続きキーパーソンとして活用することが、技能を確実に継承させるためのポイントといえます。
3.参考事例の紹介
ものづくり企業では、人材の確保に苦労している状況にあります。しかし、今後も企業が生き残り、発展していくためには、ものづくり人材の育成強化と技能継承を進めていくことが大変重要です。 2019年版ものづくり白書(PDF版)より、いくつか事例を紹介したいと思います。1)技能の見える化の推進事例
暗黙知である「匠の技」や高度な技能を、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ビッグデータなどの新技術を活用して、生産性の高い技術への転換を図ることが必要です。 継承すべき技能を、テキスト化・マニュアル化・IT化などによって「見える化」することは、技能継承にとって重要になります。 2019年版ものづくり白書(PDF版)[PDF形式:6,935KB] ≪参考事例≫■ 記録した映像から社員の作業動作を振り返る[P.218]
➡テキスト化や社員間交流による知識の共有に加え、カメラや生産管理システムの導入による数値化を図る事例■ AI による技能継承(スペシャリスト思考のAI 化)[P.219]
➡AI 技術を用いた熟練技能者の知見の可視化、構造化を図る事例■技能科学による技能継承(AR・VR の活用事例/作業のカン・コツの見える化事例)[P.220]
➡AR・VR を活用する事例2)良好な人材育成の推進事例
技能継承では、技能継承の方針を社内に浸透させ、人材育成の重要性が職場で周知されることが、実際に技能継承を推進することにつながります。 ≪参考事例≫■社員全員参加型の人材育成の取組[P.221]
➡社員全員参加型で行い、技能継承に取組む事例■1年間の研修期間を通じて各部門を経験させる人材教育[P.222]
➡多能工化などの将来を見据えた、企業内における計画的なOJTをおこなう事例■技能検定を活用した徹底した階層別教育と多能工化の推進[P.223]
➡企業内の認定職業訓練校を活用したOFF-JTをおこなう事例■伝統建築物における銅屋根職人の技能継承[P.224]
➡技能検定の活用等に取組む事例3)伝え手側の確保や質向上に向けた事例
技能継承は、単に高年齢従業員を継続勤務させるだけでなく、指導者(伝え手)として役割を付して、教える体制を整えることが重要です。 ≪参考事例≫■製造部門独自に立ち上げた技能伝承の訓練道場[P.225]
➡熟練技能者を指導者として選定する事例■OB 人材を活用した階層別研修制度の実施による技能継承[P.226]
➡熟練社員にものづくり人材の指導者となれるようリーダーシップ教育を行うほか、OB 人材を講師として活用する事例4)若者のものづくりに対する意識を高める好事例
ものづくり企業は、「若者のものづくりに対する意識を高める取組」への支援を行政に求めており、社会的に機運を高めることも重要です。 ≪参考事例≫■技能検定を用いた技能継承[P.227]
➡技能検定を目標に掲げてモチベーションの高い人材を育成する事例■名工として、後世に繋がる人材と作品[P.228]
➡技能士として知識を若い人に伝え人材育成する事例■社内検定認定制度を活用した産地全体の技能継承[P.229]
➡社内検定を目標に掲げてモチベーションの高い人材を育成する事例■ものづくりの魅力を伝える催し「燕三条 工場の祭典」[P.230]
➡地域をあげた地場産業の人づくり戦略やものづくりの価値を啓発する取組みをおこなう事例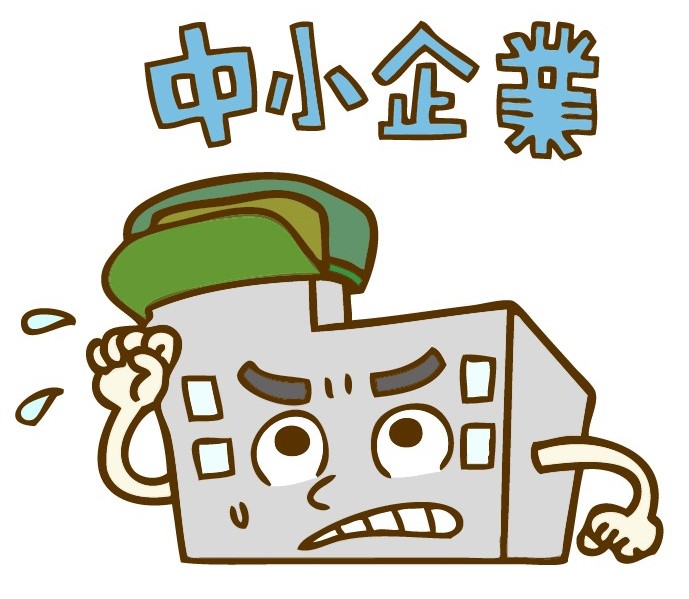
4.まとめ
一度失われると、その復活が難しいといわれている技能継承。 技能継承の重要性を社内で共有し、技能を重視する風土をつくり、技能の見える化といった継承に必要なツールや指導体制を整備するなど、腰を据えた取組みが大切ということがわかりました。 それにより、比較的短い期間で一人前の技能者を育てることができ、人材の定着につながり、企業の労働生産を高くすることが可能になります。 中小ものづくり企業の、生き残りや発展に重要な役割を果たすためにも、ものづくり人材の育成を強化していくとともに、技能継承の取組みを進めていくことが大切ですね。 今後も、中小ものづくり企業を応援していきたいとおもいます。 ]]>補助金に関するお悩みは
アクセルパートナーズに
お任せください!
補助金の対象になるのか、事業計画から相談したい等
お客様のお悩みに沿ってご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。


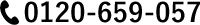
 お問い合わせ
お問い合わせ 補助金無料相談
補助金無料相談