ボスとリーダーの違いについて【~トヨタ 春闘 2020~】リーダーシップとは?
-
公開日:
私が去年これを知った時は、すごいことをやっているんだなと驚きました。
労使交渉って多くの場合が結論ありきで、全社員に公開するなんて出来ないものだと思っていました。
組合としても経営を恐れて言いたいことが言えない、こんな姿を組合員に見せるなんてことはできない、
と考えてしまいそうなことが多いのではないかと…。
しかし、動画を見て納得でした。
以前から豊田社長は、メディアや社員の前に自ら立ち、メッセージを伝えるということを
してきています。経営が見ている景色を余すところなく伝えることで、『危機感の共有』や
『目標の共有』を進め、厳しい経営環境に一丸となって立ち向かっていく組織を作り上げようと
しているのが伝わってきます。
こういう目的があった場合、労使交渉の場はまさに格好のステージと言えるのではないでしょうか。
社員が持つ疑問や不安に対して経営がどう答えるのか、なぜそう答えるのかを伝えることで、
リーダーからの強烈なメッセージを浸透させていく。とても理にかなったやり方だと思います。
社員に経営と同じような視点をもって仕事にあたって欲しいと考える場合、経営がもつ情報と同等の
情報をあますところなく社員に伝え、経営環境や経営目標を共有することが必要になります。
さらに言うと、立場が上になればなるほど『経営判断に必要となる大切な現場の情報』は
あがってきにくくなくなりますので、組織の風通しや透明性を高く保っておく必要があります。
とまあ、前置きが長くなりましたが…。
労使交渉の中で豊田社長が話しておられた、ボスとリーダーの違いについて、というお話が
印象に残りましたので、組織論の観点から考察していこうと思います。
目次
1. ボスとリーダーの違い
動画の中で豊田社長が話していた内容は、イギリスの高級百貨店チェーン「セルフリッジズ」の創業者、
ハリー・ゴードン・セルフリッジの言葉です。まずは言葉をご紹介します。
1.ボス :ボスは私という
1.リーダー :リーダーは私たちという
2.ボス :ボスは失敗の責任を負わせる
2.リーダー :リーダーは黙って処理する(失敗から学ばせる)
3.ボス :ボスはやり方を胸にひめる
3.リーダー :リーダーはやり方を教える(育てる)
4.ボス :ボスは仕事を苦役に変える
4.リーダー :リーダーは仕事をゲームに変える
5.ボス :ボスはやれと命令する(権威に頼る)
5.リーダー :リーダーはやろうという(導く)
※カッコ内にはwikipediaから引用したもの、意訳が入っています。
あとひとつ、個人的に思うところを追加させて頂きますと、
6.ボス :ボスは自分の考えと異なるものを排除する
6.リーダー :リーダーはより良いアイデアをメンバーから吸い上げる
といったところでしょうか。
部下に恐怖を与えて支配するボスと、部下の熱意を引き出して導いていくリーダー。
考えるまでもなく、どちらが企業にとって望ましい人材なのか明白ですが…。
2. ボス VS リーダー どちらが会社にとって有用?
考えるまでもないといってしまうと説得力のかけらもないので、経営理論や組織論の観点から、
それぞれのケースでどういった効果をもたらす事になるのかを考えていきます。
1.ボス :私という
1.リーダー :私たちという
この言葉の対比からは、ボスが自身の成果をあげることにフォーカスしており、リーダーは
チームで成果をあげることにフォーカスしている、という事が分かるかと思います。
それでは、なぜチームでの成果を目的とした方がいいのか、ということについて考えていきましょう。
ボスが自分ひとりの成果にフォーカスした場合、部下は自分の成果をあげるための道具として
みなされる事が多いと思います。
ひどい場合には、部下の手柄を横取りするなんてこともあるかもしれません。
短期的に見た場合、ボス個人の目標だけは達成されることが多いでしょう。
しかし、部下は極端にモチベーションを落とし、ずっとそんな事が続けば退職者も
後を絶たなくなる、なんてことも・・・。
成果報酬を導入した際に失敗する例がまさにこういった場合です。
個人の業績のみを評価基準としたら、自分の業績だけを追求することが正義になります。
そもそも企業はなぜ沢山の人を雇用し、規模を拡大するのでしょうか?
1つには、スケールメリットを追求するという理由もあるかと思います。
しかし、もっと初期の目的としては、多くの人の力を集結することで、
より大きな需要(課題)に応えることができるようになりたい
という理由があるのではないかと思います。
企業は、社会が抱える課題を解決することで、その対価として金銭を受け取ります。
つまり、人々が抱えている課題こそが『需要』であるという事ができます。
課題(需要):この大きな荷物を海外に輸出したい
解決(供給):貿易サービスというビジネスを提供する
といった具合ですね。
一人で解決できる課題なんて本当に小さなものです。だから人を雇い、それぞれの人が持つ
経験や知識を集結して、より大きな課題を解決できる集団を目指すわけです。
より大きな課題を解決すれば、当然受け取る対価も大きくなります。
多様な知識や経験を集結して、より大きな課題を解決していこうとしたら、メンバーの能力を
最大限に引き出すことが一番望ましいですよね。だから、『私たち』と普段から言えるような
リーダーが望ましいという訳です。
2.ボス :失敗の責任を負わせる
2.リーダー:黙って処理をする(失敗から学ばせる)
この対比からは、一見ボスの方が正しいんじゃないかと思われる方もいるのではないかと思います。
確かに自分の失敗の責任を負うのは当たり前のことです。しかし、ここでは『失敗』の定義について、
額面通りではない意味が込められていた様に思います。
動画の中で豊田社長が話していた『失敗』とは、単純な『ミス』の事を言っているのではなく、
挑戦をした結果による失敗を指している様に感じました。その前提で話を進めていくと、ここでいう失敗とは
『挑戦』をしなければ起こらないことになります。
仮にここでボスのようなマネジメントが、部下の失敗を咎め、責任をとらせようとした場合どうなるでしょう?
今後は失敗しない方法を選択しますよね?つまり部下は『挑戦』をやめてしまいます。
上司に失敗を咎められ、さらに責任を取らされたあげく「◯◯くんは挑戦をしなかった」
などという評価をされてしまったら、モチベーションが下がるどころの話ではなくなるかもしれません。
経営の神様と呼ばれる松下幸之助氏の言葉で
「失敗したところでやめてしまうから失敗になる。
成功するところまで続ければ、それは成功になる。」
というとても有名な言葉があります。挑戦からしか新しい価値は生まれません。
不確実性の高まる現代において、「ボスではなくリーダーたれ」という意図は
「部下が挑戦しやすい風土をリーダーとして作ってください」と言っているのだと思います。
3.ボス :やり方を胸に秘める
3.リーダー:やり方を教える(人を育てる)
ボスはあくまで自分個人の業績にフォーカスしています。ボスまで昇りつめた人となると、
自身が成績を上げるためのスキルはきっと高いのでしょう。
しかし、そのスキルを部下に伝えてしまうと、他の社員との差別化ができなくなり
自身が霞んでしまいかねません。
しかし会社からすると、ボスの持つ優位なスキルが、個人のみに依存している状態は望ましくありません。
スキルを部下に伝え、会社全体として大きく業績を伸ばす方がいいに決まっています。
でもボスの気持ちもわかります。
苦労して身につけたスキルを部下に教えたおかげで、自分の評価が相対的に下がってしまう、
となるのであれば誰もがボスになってしまいそうです。
解決方法はそんなに難しいことではありません。
「優秀な部下を育てた」という評価の比重を、業績評価よりも大きくしてしまえばいいのです。
さらにいえば、業績評価の項目にチーム単位での評価を加えることで、会社は「上司が部下を育てる
ことに重点を置いているんだ」というメッセージをより強烈に伝える事ができるようになります。
4.ボス :仕事を苦役に変える
4.リーダー:仕事をゲームに変える(熱意を呼び起こす)
5.ボス :やれという(権威に頼る
5.リーダー;やろうという(導く)
ここでは最初に、リーダーの役割を明らかにしていきたいと思います。
リーダーシップの役割
著書「7つの習慣」で有名な、スティーブン・R・コヴィー博士は、著書の中でマネジメントと
リーダーシップの役割を明確にしています。
“リーダーシップは望む結果を定義しており、何を達成したいのかを考える。”
リーダーシップとは、目標そのものを明らかにするものだと言っています。
著書に分かりやすい例えが載っていたので少し抜粋させて頂きます。
ジャングルで森を切り開く作業を行っているチームの例えです。
・作業チーム :生産に従事し、現場で問題を解決する人たちで、
彼らは草を刈って道を切り開いていく。
・マネジメント:その後方にいて、斧の刃を研ぎ、方針や手順をきめ、筋肉トレーニング
を開発し、新しいテクノロジーを導入し、作業スケジュールを作る。
・リーダー :ジャングルの中で一番高い木に登り、全体を見渡して
「このジャングルは違うぞ!」と叫びメンバーを方向付ける。
リーダーとは、日常業務の喧騒から少し離れたところから内部と外部の環境を見極め、
チームの進むべき方向に動機づけをしながら導く人の事です。
プロジェクトのリーダーに任命された人は、プロジェクトを成功させるために
一生懸命考えると思います。
プロジェクトを成功に導くためには、まず最初に目標や危機感を共有し、チームに
一体感を生み出し、動機付けをする必要があります。
より良い成果をもたらすために、メンバーの意見を尊重・共有し、心理的安定性を
高める雰囲気を作ります。そして、目標達成のために最適なやり方を模索して、
PDCAサイクルを回し進捗を管理する。
※下線部分は7つの習慣ではマネジメントの役割と定義されますが、優秀なリーダーはこの部分も
兼ねているんじゃないでしょうか
リーダーシップという言葉は、ある目標に対して主体的に取り組む際、そのリーダーが
一生懸命考え抜いた末にとった理想的な行動のことを総称する言葉だと思っています。
さて、上記で説明した通りリーダーの役割というのは、マネジメントの様な日常業務の
一つ上にいなければなりませんので、会社組織で言えば経営の役割ということになりますね。
マネジメント層やチームメンバーを動機づけて燃え上がらせる、これは経営でなければ
できない仕事になります。
翻ってボスは仕事を苦役に変える・・・というのは、仕事の意味を理解させずに
ただ上から「やれ」と命令をするからですね。
それがなぜ良くないのか、動機付けに関する理論を使ってお伝えしていきます。
動機付け理論のひとつとして、心理学者のハックマン、経営学者のオルダムによって
提唱された職務特性モデルという理論があります。これは、仕事自体の特性によって
動機づけが成されるというものです。
職務特性モデルでいう仕事の特性とは
①技能多様性 :自身の持つ技能をどれだけ沢山活用できる仕事なのか
②タスク完結性 :計画、調達、生産、販売、顧客満足まで全てに関われるか
③タスク重要性 :社会や自社に対する重要性を認識できる仕事かどうか
④職務自律性 :自身で裁量を持って進められるかどうか
⑤フィードバック:業務そのものから手ごたえを感じられるかどうか
つまり、メンバーを動機づけるには、「なぜその仕事をやるのか」ということを理解しており、
それに対して「裁量を持ってとりくめる」という状態が必要なわけです。
ボスからただ「やれ」と命令されてやる仕事では、ほとんどの職務特性を満たすことができません。
やっている仕事の意味もわからないのに、モチベーションなんかあがりようがありません。
つまり、ボスが仕事を「苦役」に変えるのは、作業をこなすがごとく仕事を与えて
それを実行するメンバーのモチベーションをあげないから、という事になります。
6.ボス :自分の考えと異なるものを排除する
6.リーダー:より良い考えをメンバーから吸い上げる
これは、私が付け加えたものなのでセルフリッジの言葉に比べると、大幅に価値が
劣るとは思いますが・・・。
上記のリーダーシップを明確にした項では、リーダーはより良い成果を生み出すために
メンバーの意見を尊重し、引き出すための風土を作ると述べました。
自分の意見がチームに反映されてうれしくない人なんていないですよね?
そしてこれは、「職務特性モデル」でいう「職務自律性」のところに関係してきますし、
Googleの研究によって導き出された「心理的安定性」をもたらすことにもつながります。
逆に、ミーティングの中で「お前の意見はくだらない」、「少しは考えてから発言しろ」
などと言われてしまったら、ほとんどの人が発言をしなくなっていってしまいます。
一見くだらないと思える意見に対しても、ほかの人からの質問や意見が入ることで、
素晴らしいアイデアに昇華されるケースは往々にしてあります。
「自分の考えと異なるものを排除」するということは、チームで仕事をする意味や
多様性を活かす機会を自ら放棄することにつながります。
※あまりにも無意味な議論に時間を費やす無駄は省く必要があるので、リーダーのファシリテーションが
非常に重要になります。無限に風呂敷を広げていてはキリがないので公正な線引きも必要になるかと思います。
リーダーの役割はものすごく大変ですが、求められている能力は専門性ではありません。
メンバーと仕事の意味を共有し、動機づけ、一丸となって取り組める雰囲気を作って
成果を出すことが求められています。
いかにメンバーの力を余すところなく引き出すかという能力が問われるのかなと思います。
不確実性の高まっている現在、未来を見通すのはとても難しいです。
そして世の中を変えているのは、消費に対する多様な価値観と、それに答えようと
チャレンジする人たちの存在です。
であれば、企業が生き残るためには社内の多様性を活かして未来を切り開くほかない
ということになるかと思います。
社内の多様な価値観や知識、経験を活かすにはボスとリーダーのどちらが望ましいのか。
ここまで散々書いてきた通り「リーダー」ですね。
こういった理由から、豊田社長は労使交渉の中でこんなお話をされたんじゃないかと推察します。
3.会社と労働組合のありかた
最後に、今回のコラムのテーマにも入っている労使交渉、労使の在り方について考察していきます。
皆さんは生産性三原則という労使の根幹をなす考え方をご存知でしょうか?
昔の労働争議は現在とは比べ物にならないほど強烈なもので、三井三池争議のように
ストライキが100日以上に及ぶような強硬なものも沢山ありました。
時には暴力が使われることもあったようです。
しかし、長期間にわたる強硬な団体行動権の行使は、労使ともに疲弊して誰も
得をしない結果になることがあります。
三井三池争議では、ストライキ中に多くの離脱者を生み、退職あるいは新しい労働組合の
結成に至りました。日鋼室蘭争議のように、争議中に会社自体が倒産して全員が
泣くことになるといった痛ましい事件もありました。
こういった反省から、次第に三井三池争議で見たような労使協調の労働組合が
結成されていく事になりました。
当時の新しい労働組合は、労使双方の幸福を目的とするものであったため、
生産性三原則を体現するものであったようです。
生産性三原則
この三原則は、経済界・労働界・学識者の三者が共同で掲げたもので、生産性運動の推進には
労使の協力が不可欠との強い思いが反映されています。
生産性向上の目的は主に国民の生活水準の向上にあります。
・雇用の維持・安定の原則
雇用の維持・安定は経済社会を安定させることに寄与するという理念です。
・労使協議の原則
労使は対等で、互いに協力し、話し合って(協議)、良好なコミュニケーションを
維持することが大切だという理念です。
・成果配分の原則
人間が考えて社会を豊かで快適なものにするために作った企業なんだから、
その活動の成果は公正に配分しましょうという理念です。
つまり、雇用を守るかわりに、労使みんなで協力して企業の生産性を向上させましょうね、
そこで生み出した付加価値はみんなで分け合い、みんなの生活を豊かにしましょうという考え方です。
日本の高度経済成長を大きく支えた考え方だと思います。
現代では、少しずつ失われてきている考え方じゃないかと感じます。
アベノミクス発動に関与した学者の中にも、この三原則が守られていないから経済が
回らなくなっているんだ、と指摘しておられた方もいらっしゃいました。
しかしながら国民の生活水準がある程度満たされたいま、生産性を向上させる事への目的が
あいまいになってしまった事は事実です。
何をもって生産性を高めることへの必要性を伝えればいいのか、経営はその問いに対する
答えを持っている必要があるかと思います。難しい時代です。
さて、以前コラムの中でお伝えした豊田社長の発言、
「会社は従業員の幸せを願い、組合は会社の発展を願う。
そのためにも、従業員の雇用を何よりも大切に考え、労使で守り抜いていく」
という言葉ですが、上にある生産性三原則と同じですよね?
私は、会社にとって人こそが全てだと思っています。
会社と従業員は運命共同体です。
だからこそ、こんな考え方でお互いの将来のためとなる議論ができたら、
とてつもないパワーを生み出すことが出来るんじゃないかと思います。
ここ30年ばかり少し元気のない日本ですが、どんな団体にあっても
こんな考え方に立って前進していけたらいいなと願っています。
この記事の監修

中小企業診断士有資格者
株式会社ai-soumu代表取締役 上瀬戸研次
18年間中堅企業の経理総務と情報部門に従事し、現在はクラウド会計システムなどを用いて経理総務のアウトソーシングやIT導入補助金を利用したシステム販売・導入を行う。モットーは「しなければならないことを減らし、やりたいことを増やす」で、顧客が望むことに時間を使えるよう支援することを目指している。
株式会社ai-soumuについて詳しくはこちら補助金に関するお悩みは
アクセルパートナーズに
お任せください!
補助金の対象になるのか、事業計画から相談したい等
お客様のお悩みに沿ってご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾
WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。


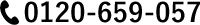
 お問い合わせ
お問い合わせ 補助金無料相談
補助金無料相談